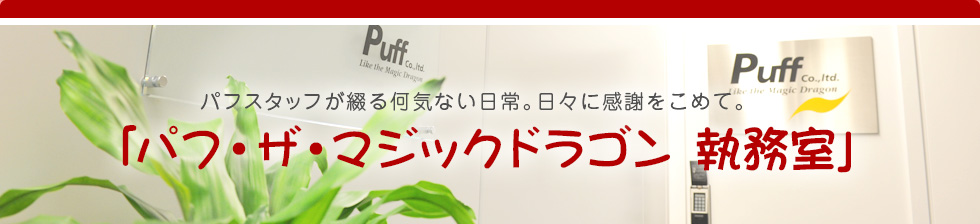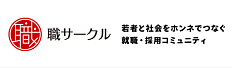若手社員との向き合い方
2018年7月26日 (木曜日)
やってきました、第61回かほログ!
咳に苦しんで一か月、なかなか治りませんね…。
人の心配している場合じゃないのかもしれませんが、
お客様からも、「咳が止まらなくて」とか
「夏風邪が社内で流行っていて」というお話を最近よく耳にするので
皆さまお気を付けくださいませ。
―――
さて、先日お客さまとこんな話をしておりました。
近年の新入社員はすごく良い子なのに
入社してその良さを発揮しきれていなく、
型にはまってしまうように思う、なぜだろう?
バリバリ働いてすぐにでも輝きそうな子でも
なにかストッパーがかかっているような感覚だ、と。
すぐにはその答えがわからなかったのですが、
話をしていくうちに、
「正解を求めすぎているのではないか」
「新入社員個々人が思う“社会人としてあるべき姿”に縛られすぎているのではないか」
という話になりました。
「~でなければならない」
「~せねば!」という責任感を大きく抱いているのではないか、と。
たしかにそうかもしれない、と思いました。
実際周りの若手社員を見ていても、それに近しいことはありますし、
先日は、今年から社会人となった妹から
「有休は新入社員が入社後すぐの夏にとってもよいものなのか」
「何を理由に取ったらいいのか」
といったお悩みLINEメッセージがひたすら飛んできました。
もっと自由でいいのに、
もっと思ったことをそのまま発言したり行動したりしてもいいのに、
もっとたくさん失敗したっていいのに、
と私は思ってしまうんですが、きっとそれは私の世代の話であって、
彼らには彼らの育ってきた環境が影響しているんだろうなと思います。
(そんなことを言いながら、私にもどこかその節はあるのではないかと
ふと思います。)
いつかもブログに書きましたが、
・目の前に大量の口コミがある時代
・ググれば答えが出てくる時代
・マニュアルが備わっている時代
なので、意識してそうなっているというよりも、
それが自然に備わっているのかと。
となると、何かしら、組織の仕組みや研修、交流の中で
「正解が必ずしもあるとは限らない」
「自由な発想が許される」
「上司も実は過去にさんざんしくじってきた」
といったような情報を得られるとよいのでは、と思いました。
同じ「若手社員」、「就活生」であっても
やはり一年ごとにその志向、傾向は変わっていくのだな、と感じます。
その変化を毎年キャッチアップしていこうと改めて思いました。
―――
お次は大岡さんです!