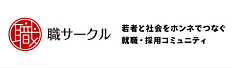幼いころを思い出してみる(3)
2014年10月28日 (火曜日)
5月の初夏の陽気の日だった。幼稚園が終わり、いつもどおり帰りのバスに乗った。
なんだかボウっとしていた。バスを降りて家まで歩いていた。自分の影がゆらゆらと踊っていた。自分の頭もくらくらしていた。
「あれ?なんだかおかしいぞ」。自分でも気が付いていた。
フラフラしながら自宅までやっと辿り着いた。でも、母親は勤めに出ていて家には誰もいない。玄関の土間から靴を脱いで部屋に上がり込む力はすでに残っていなかった。
ここでいったん記憶は途切れる。
目が覚めた時には布団の中にいた。片側には白衣をまとったお医者さんと看護婦さんがいた。そして反対側には心配そうに覗きこむ母親の顔が見えた。
本当に不思議なのだが、この目覚めた瞬間の景色は、この50年近くずーっと頭の中に焼き付いている。
病名は、あとから知ったのだが、はしか(麻疹)に罹っていたのだ。倒れた日から数えて完治するまで2週間ほどかかった。
久々に幼稚園に行けることになった日のこと。季節は、もうすっかり夏になっていた。
病み上がりということもあり、母親が仕事を休んで付き添ってくれた。
緊張しながら幼稚園の門をくぐった。
園児たちが遊んでいる姿を見てショックを受けた。僕が着ている制服と違うのだ。
僕がはしかで休んでいる間に衣替えとなり、制服制帽が夏物になっていたのだが、そんなこと5歳の僕が知る由もなく、悲しくて泣きだしそうになった。
教室に入った。なんだか皆がよそよそしく感じた。
でも、先生は久々に登園した僕を見て喜んでくれ、制服の違いで受けたショックも和らいできた。
しかし、その数分後、さらなるショックを受けることになる。
先生がオルガンを弾き、園児全員での「朝の唄」が始まったのだが、僕の知らない唄だった。僕が休んでいる間に教えられたと思われる「新曲」だったのだ。
一生懸命、他の園児の口の動きを真似しながら歌おうとするのだが、ついていけない。悲しくて悲しくて、ついに僕はワンワン泣き出してしまった。
大泣きしている僕を見て、先生はやっと気が付いてくれた。オルガンを中断して、僕のところに駆け寄って来た。
「ごめんね、クギサキ君、この歌まだ知らなかったんだよね、ごめんごめん」
母親も、僕の泣き方があまりに酷かったので、心配そうに駆け寄ってきて頭をなでてくれた。
どうってことのない5歳児の1シーンなのだが、人間というのは不思議なもので、こんなことを50歳を過ぎた今でも覚えているのだ。
(次回に続く。明日は書けるかなあ…)