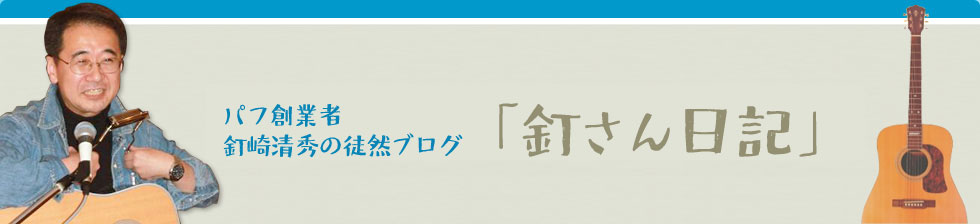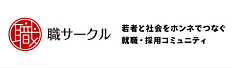幼いころを思い出してみる(17)
2014年11月26日 (水曜日)
憧れの黒帯を手に入れるために受けた昇段試験。しかし、その黒帯を手に入れるためには3人の選手と戦って勝ち越さなければならない。
僕の対戦相手は警察学校に通う警官見習い2名と高校生1名。中学2年生の僕からは、とてつもない巨人に見えた。
対戦が始まった。
最初の対戦相手が警官見習いだったか高校生だったかは覚えていない。
覚えているのは「始め!」の審判の合図で組んだ瞬間、僕の体が宙に舞って畳に叩きつけられたこと。
あっというまに一本取られてしまった。ぜんぜん相手にならないとはこのことだ。
二人目との対戦。残念ながら記憶に残っていないのだが、負けたのは間違いない。
そして、忘れもしない三人目との対戦。相手は警官見習いのゴツイ大人だった。
僕はすでに2連敗していたので、もう黒帯の可能性はなくなっていた。戦意喪失の状態だ。
せめて一矢を報いたい…なんていうことは考えていなかったのだが、投げ飛ばされて痛い思いだけはしたくなかった。
だから僕は腰を思いっきり引いた逃げの姿勢をとっていた。警官見習いは足を飛ばしたり投げを打とうとするのだが、逃げに徹している僕には技がかからない。
僕が逃げてばかりいるので警官見習いも頭に来たのだろう。僕をブンブンと力任せに振り回す戦法に出た。
畳の上をぐるぐるぐるぐる。目が回るくらいに振り回された。
そして次の瞬間、浴びせ倒しをくらった。
警官見習いは僕を羽交い絞めにして抑え込む。静かに抑え込んでくれればいいものを、けさ固めしながら体をぐるぐるぐるぐる回転させる。僕の右腕は、そのたびに畳に強烈に擦り付けられていた。
30秒が経過して、抑え込み一本。
負けを告げられた後、審判から「大丈夫か?」と声をかけられた。僕の右腕からは血が滴っていたのだ。柔道着の裾をまくってみて自分の目を疑った。右腕が真っ赤っか。酷い火傷をしたように皮が剥けて腕全体が充血していた。
情けない敗戦だった。
こんな負け方をするくらいなら、素直に投げ飛ばされておけばよかった。
大分市から湯布院に帰る汽車の中で僕は放心状態だった。
試験会場で応急処置をしてもらった右腕。ぐるぐる巻きの包帯の下からジンジンとした痛みが襲ってきていた。
「くそっ、もう柔道なんか辞めてやる!」
その日の夜は、悔しいのと情けないのと痛いのとで、一睡もできなかった。
幼いころを思い出してみる(16)
2014年11月25日 (火曜日)
昇段試験は、筆記試験と実技試験からなる。筆記試験は、柔道修行の目的とか技の種類を書いたりとか、ごくごく簡単なもの。前日に予習をすれば、よほどのおバカでないかぎり満点が取れるもの。
実技試験は、形の演技と試合からなる。形の演技は僕は比較的得意だった。肩車とか背負い投げとか。いまでもできるんじゃないかな。
問題は試合。
4人1グループとなり総当たり戦を行う。ここで勝ち越すことが、段位を取得するための絶対条件となるのだ。
弱い選手たちとの組み合わせであればラッキーなのだが、運悪く強い選手がグループの中に2人いると負け越しが決まってしまう。どういう組み合わせになるのかは、当日まで分からない。
僕が割り当てられたグループは、警察学校に通う大人(警官の見習い)が2名、高校生1名、そして僕。
おいおい、なんだよ、なんだよ……。
いままでは中学生同士でしか試合をしたことがなかったのに、いきなり高校生や大人との対戦。しかも、3人ともごっつい体つきである。
僕は試合前から完全にビビりまくっていた。そして、昇段試験を受けるなんて言ったことを後悔した。
でも、いまさら逃げ帰るわけにもいかない。
僕は足をブルブルガクガク震わせながら、警察学校生と高校生との戦いに臨んだ。
幼いころを思い出してみる(15)
2014年11月21日 (金曜日)
「クギサキ、お前は柔道をやるために生まれてきたようなもんじゃの、練習を続けていたらそのうち強くなるぞ、ガハハ」
・・・と、言われてその気になって、つらい練習にも耐えながら数か月が過ぎていた。
しかし、一向に強くなった自覚がない。
先輩と乱どり稽古(実際の試合のような練習)をしても、いつもコテンパンにやられるばかり。勝てたことなんて一度もなかった。
そんな僕も2年生になり、大会に出なければならない日がやってきた。大分郡の大会で、僕は個人戦に出場することになった。
結果は、惨敗。
詳しい試合内容は忘れてしまったが、とにかくあっという間に投げられたという記憶がある。
弱さを実証してしまった僕は、以来、試合に出ることはほとんどなくなり、もっぱら補欠選手となる。まあ気楽と言えば気楽なのだが、やはり悔しいという気持ちもあった。
柔道といえば、やっぱり黒帯。
黒帯を締めた柔道着姿には、こんな弱い僕でも、強い憧れを抱いていた。
大分県では夏と冬の2回、昇段試験が行われていた。
中2の1月か2月ころだったと記憶している。僕は、昇段試験を受けることにした。
当時の同期部員たち(たしか僕を含めて7名いた)も全員、昇段試験を受けるために、遠く大分市まで朝いちばんの汽車に乗って出かけて行った。
試験場は、大分市内の大きな体育館。
いかにも強そうに見える柔道家たちが、ぎっしりと詰めかけていた。
(果たして黒帯はとれるのか?)
幼いころを思い出してみる(14)
2014年11月20日 (木曜日)
「柔道一直線」に影響を受け、一条直也や車周作のようになりたくて門を叩いた柔道部。でもドラマのように人をホイホイ投げ飛ばすなんてことはできず、厳しく苦しい毎日が続くことになった。
スポ根の時代である。練習は月曜日から土曜日までの毎日。放課後すぐに始まり、終わるのは日暮れ遅く。開始の際は準備体操として、腕立て伏せと腹筋は最低でも100回ずつ。あと腹ばいになって腕の力だけでの匍匐(ほふく)前進のようなことを50メートルくらい行っていた。
これがきつかった。
それまでろくに運動なんてしたことのなかった僕の体は悲鳴を上げて、腕がまったく上がらなくなった。服を脱いだり着たりすることもできない。肘や膝は擦り剝けて血だらけ。
最初は10人以上いた新入部員も1週間が過ぎたころには半分くらいに減っていた。
僕もよっぽど辞めようかと思ったのだが、なぜか続けていた。
母親に無理言って安くない柔道着を買ってもらった手前、すぐに辞めてしまっては申し訳ないという気持ちもあった。
柔道部の顧問の先生から、目をかけられていると勘違いしていたことも大きかったのかもしれない。
顧問は、飯倉巌先生といって、名前もそうだが、全身から威厳を感じさせる先生。大分県の柔道界では有名な指導者だった。
入部して間もないころ、この飯倉先生から「クギサキ、お前は柔道をやるために生まれてきたようなもんじゃの、練習を続けていたらそのうち強くなるぞ、ガハハ」と言われていた。
純粋だった僕は、先生のそんな根拠のない言葉を信じてしまったのかもしれない。
(続く)
幼いころを思い出してみる(13)
2014年11月19日 (水曜日)
1973年4月。僕は湯布院町立湯布院中学校に入学した。
当時の中学校の校舎には新校舎と旧校舎の二棟があったのだが、1年生の校舎は旧校舎。もう信じられないくらいオンボロの木造校舎で、歩くとギシギシ鳴って床が抜けるんじゃないかと思うような古さだった。
前回書いたように、僕は入学式の翌日には柔道部の門を叩いた。
柔道部はなぜだかすごい人気。たしか一年生の新入部員は10人以上いたのではないだろうか。「柔道一直線」に影響を受けていたのは僕だけではなかったのだ。
柔道部の写真だけアップして、詳しい話はまた明日(以降)、書くことにしよう。
幼いころを思い出してみる(12)
2014年11月18日 (火曜日)
小学生時代の、忘れられない出来事をひとつ書き忘れていた。
カラーテレビが初めて我が家にやってきた日のことである。
忘れもしない。1970年12月31日の出来事だ。
大晦日である。小学4年生だった僕は、ウキウキドキドキしていた。
何にウキウキドキドキしていたかというと、その日の夜の「レコード大賞」と「紅白歌合戦」に対してである。
僕はテレビっ子で歌謡曲が大好きだったのだ。
夕方になった。
年の瀬の街の様子を伝えるニュースが我が家の白黒テレビから流れていた。
プツっ。
という音がしたかどうかは定かではないが、突然画面が真っ黒になった。
バンバンバンと叩いても、ガンガンガンと蹴飛ばしても、テレビはうんともすんとも云わない。
それまでも真空管が切れてテレビが映らなくなることは何度もあった。そのたびに町の電気屋さんを呼んで修理してもらっていた。
もちろんこの日も、町の電気屋さんに来てもらった。
電気屋さんは、テレビを横に倒し、裏側のパネルを取り外して分解し、いろいろと調べている。
僕も母も兄も、病気になったペットを見守るかのように、その修理の状況をじっと見ている。
そうこうするうちに、大晦日の仕事を終えた父親も家に帰ってきた。
電気屋さんが、「うーん、こりゃあちょっと今夜中に直りそうもねえで。どげえしょうか?」と、絶望的なことを言う。
一瞬、気まずい沈黙の時間が流れた。
が、次の瞬間の父親の言葉。
「しょんなかね。新しかテレビば買おうか。せっかくならカラーテレビにしようかね」
我々は一転、天にも上るような気持ちになった。
まさか、貧乏な我が家にカラーテレビがやってくるなんて……。
僕は喜びを噛みしめていた。
万博に連れて行ってもらえず悔しくて大泣きした1970年だったのだが、急転直下、嬉し泣きするような出来事で終えられることになったのだ。
町の電気屋さんは、いそいそとカラーテレビを車に積んで再度やってきた。
とてつもなく大きく感じた。たしか18インチかそこらのブラウン管のサイズなのだが、当時のテレビの筐体はその何倍もの大きさだったのだ。
すでに夜8時を回っていた。レコード大賞はクライマックスのシーンを迎えていた。
この年のレコード大賞は、菅原洋一の「今日でお別れ」。
まさに、それまでのオンボロ白黒テレビとお別れした日となったわけだ(笑)。
「我が家も文化的な暮らしのでくるようになったねえ……」と、紅白歌合戦を観ながらしみじみと、しかし少し誇らしげに語っていた父親の姿を今でもよく覚えている。
(次回はホントに中学時代ね)
幼いころを思い出してみる(11)
2014年11月17日 (月曜日)
さて、そろそろ小学校を卒業して中学校に入学してみようかと思う。
僕が通っていた小学校は、由布院小学校。そして中学校は、湯布院中学校。
お気づきだろうか。「ゆふいん」の「ゆ」の字が違う。小学校は「由」で、中学校は「湯」なのだ。
湯布院町は、昔は「由布院町」だったのだが、その後「湯平村」と合併したことで、「湯布院町」となった。
小学校には旧由布院町の子供たちが通い、中学校には旧由布院町に加え旧湯平村の子供たちが通うことから、「湯布院中学校」の字を使うようになった(と解釈している)。
1973年4月。
僕は、ピカピカの黒い制服を着て中学校の入学式に臨んだ。
そして頭は、坊主頭。
中学校の校則で、男子生徒は必ず坊主頭にしなければならなかった。
小学校卒業直前、ものすごく恥ずかしかったのだが、床屋に行って丸刈りにしてもらった。
このころの写真を探してみたのだが見つからなかった。相当に初々しい顔をしていたのではないかと思うのだが、残念。
中学入学後、僕はすぐに柔道部に入部した。
中学に入ったら柔道部に入ろうと、小学生のころから決めていた。「柔道一直線」というTVドラマの影響を強く受けていたのだ。
可愛い奴だ。
(このシリーズ、12月初旬まで続けますね)