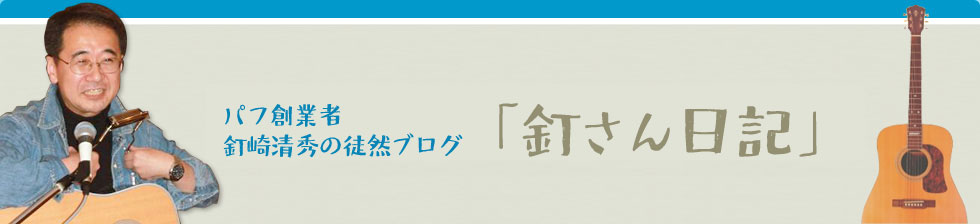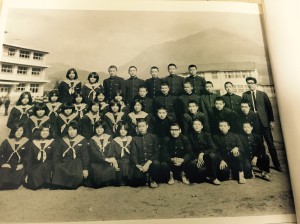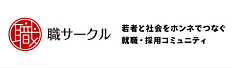夢は夜ひらく
2014年12月11日 (木曜日)
というタイトルがふと浮かんだのだけど、あまり意味はない。
最近(いや昔から)夜が長い。冬至が近づいているから?いやいや、そうじゃない(笑)。
昨夜も、お湯割りを飲みながら、野郎だけでしみじみと。
いくつになっても語り合うことは大事である。
赤く咲くのはけしの花、白く咲くのはゆりの花だけど、
もうひと花、どんな色で咲かせましょうかね。
釘さんの夢は夜ひらく……。
では、朝食&マッサン後、行ってきます!
ふつうの日記に戻る日
2014年12月9日 (火曜日)
思い出語りの日記が長く続いたせいで、日常のできごとの記録がおろそかになってしまった。
この1か月半、いろんな変化があった。
いちばんは秋から冬になったこと(^_^;)。
それからウルトラインターンシップ100×10チャレンジ【秋=第二クール】が、いよいよ終盤を迎えつつあること。
第二クールは想定外のことがいろいろと起きており、なかなか苦戦している。
来週末(20日の土曜日)がいよいよ成果発表会。そしてその翌日(21日の日曜日)がBIZオーディション。さて、どんな逆転ドラマが生まれるだろうか。
楽しみにしておこう。
次の変化は、お腹の成長が止まらないこと。
そんなに暴飲暴食しているつもりはない。ランニングも昔ほどではないが、週末にはいつも走るようにしている。
でも、お腹の成長は著しく、衣替えした際の秋冬用のスーツのズボンがキツイ。ベルトがなくても十分なくらい(´・_・`)。
最後はやっぱり、マッサンかな。
いやあ、このドラマは楽しい。見ててイライラするんだけど、それがなかなかいい。
サントリーの創業者をモデルにした堤真一の演技が秀逸だ。さすが鈴木オート。
エリーちゃんの一生懸命さも伝わっていい。だんだん日本語が下手になっていくのだが、それがまた意地らしくてガンバレと応援したくなる。
と、どうでもいいことを書き綴る日記。
また明日からボチボチと駄文を重ねていくことにしましょう。
では、朝食&マッサン後、行ってきます!
幼いころを思い出してみる(最終回)
2014年12月8日 (月曜日)
柔道部でのドタバタを中心に中学生のころのことを書いてきたが、もちろん柔道ばかりをやっていたわけではない。
中学の三年間というのは、もっとも多感な時期である。いろんなことがあった。
●中学一年生
本格的に異性に目覚めた。朝から晩まで女性のことばかり考えていた(笑)。
フォークソングを好きになったのもこのころだ。南こうせつとかぐや姫(これが正式なグループ名だった)の代表曲となる「神田川」がリリースされたのは、中一の秋だった。ほかにも井上陽水、吉田拓郎、チューリップ、アリス、ガロ、海援隊などなど、ラジオでよく聴いていた。
ラジオと言えば深夜放送に嵌っていったのもこのころ。鶴光のオールナイトニッポンは毎週土曜日のお楽しみだった。教科書や参考書を広げつつ、勉強などいっさい手につかなかった。
●中学二年生
柄にもなく学級委員を務めていた。クラスには問題児が何人もおり(根がわりとまじめだった僕は)クラス運営に苦労していた。
ひとつだけ忘れられないことがある。夏の臨海学校で級友が溺れて亡くなってしまったことだ。
その級友と僕とは仲が良く、臨海学校の前日も一緒にビーチサンダルを買いに行ったりしていた。気が弱く、クラスの悪ガキたちからよくいじめられていた級友だったのだが、僕といるときは逆に僕が彼から、からかわれたりしていた。彼にとってはホッとできるひと時だったのではないかと思う。
溺れたのは、彼が悪ガキたちに誘われて一緒に泳いでいた時だった。何があったのかは分からない。ただ、僕とずっと一緒にいたならばと、大いに悔やんだ。葬式で弔辞を読んだ僕は泣きじゃくってしまい、ほとんど言葉にならなかった。辛かった。このことを公の文章にするのは、これが初めてである。
もうひとつ書き残しておきたいことがあった。
僕は比較的温厚な性格だったのだが、中二の秋に、母や教師と激しくぶつかったことがある。
昔から口やかましい母だったので、僕はいつも母の言うことを「はいはい、はいはい」と言って、右から左に流すようにしていた。
二学期の技術家庭の授業で、カンナやノコギリなどが入った大工セットを買わなければならないことがあった。たぶん、そのころ我が家にはお金がなかったのだろう。母は「そげなもんは買わんでもよかっ!」といって取り合ってくれない。全員が買う必要のあるものだと、どんなに説明しても「学校にあるのを借りればよかったい。無理やり生徒に買わせる学校がおかしかと!」と言うのみ。
結局、技術家庭の先生に「うちでは買ってもらえないから学校のを貸してほしい」と頼んだところ、「お前にだけ貸すわけにはいかん。ふざくんな!」と一喝された。そのとき、どうやら僕は反抗的な態度を取ったようで、先生からいきなり殴られた。訳が分からなかった。皆の前で殴られたのである。学級委員としてのプライドもあった。先生を思いっきり睨み付けた。すると先生は、僕の顔が腫れあがるくらい、さらに何回も殴りつけた。僕は泣きじゃくった。痛いからではない。悔しかったのだ。恥ずかしかったのだ。そして、ノコギリを買ってくれない母と貧乏を恨んだ。この日の悔しさと恥ずかしさは、やはり一生忘れることがないだろう。
●中学三年生
中学の締めくくりとして、最高の教師や級友たちと巡り合えた。
このころの級友とは40年経った今でも交流がある。
渡辺浩という当時の生徒会長で僕の最大の敵(悪友)だった男は、高校時代も大学時代も社会人になってからも、そしてなぜか今現在も、僕の回りをウロチョロしている。来週も、会いたくもないのに会う約束をしている(笑)。
イオちゃんという当時の愛らしい副班長は現在、湯布院で福祉の仕事をしており、数年前から介護が必要となった母の心配をしてくれていた。ことあるごとにメールで近況やアドバイスを僕に送ってくれていた。
永遠のマドンナきよさんは、いまでも僕の誕生日にバースデーメッセージを送ってくれる。つい先日も54歳の誕生日にもらったばかりだ。ちょっとだけキュンとした。できれば40年前にもらいたかった(#^.^#)。
姫野はガソリンスタンドを経営する社長だ。帰省した時はいつもこのガソリンスタンドに顔をだし、「おう元気か?じゃまたな!」と1分間だけ会話することにしている。それだけで十分だ(笑)。
潤一郎は、大手の航空会社で整備士をやっている。消息が一時途絶えていたのだが、4~5年前に同窓会で再会して以来、年に一度は会っている。あいかわらずスケベだ(爆)。
他にもまだまだ仲の良かった級友たちがたくさんいるのだが、切りがないのでこのへんで。
そして、担任の中島先生は怖かったけど、僕に大きな影響を与えてくれた先生だった。こういう大人になりたいと、15歳の僕に思わせてくれた。殴られたりビンタされることもあったけど、理不尽に殴られることはなかった。いつも納得のいく、愛ある体罰だった。
この先生やクラスのことは昔(15年ほど前)、メルマガに連載していた「パフの創業物語」のなかで書いたことがある。
中二のときは辛いことの多い毎日だったのだが、中三のときは本当に毎日が楽しかった。本来であれば高校受験を控えた大変な一年のはずなのだが、いま思い出されるのは楽しいことばかり。
中島先生と素晴らしい級友たちが作りだした「三年一組」には、いまでも感謝している。
その中島先生は、7~8年ほど前に病気で亡くなった。翌年、悪友の渡辺浩といっしょに帰省して墓参りに訪れたのだが、先生はきっと喜んでくれたことと思う。
そして湯布院中学校を卒業し、僕は大分市内の高校に進学。一人暮らしを始める。
以来僕は、両親と一緒に過ごすことがほとんどなくなった。長期の休みの時も、ほとんど自宅には寄り付かなかった。高校を卒業して、東京に行ってしまってからはなおさらだ。
だから親孝行らしい親孝行を、僕は何もしてこなかった。一緒に暮らすことが親孝行だとするならば、それすらもしてやれなかった。
僕の父は今から23年前、心臓の発作で急逝した。享年62歳という若さだった。
そして母はつい先日、脳梗塞が原因で亡くなった。享年90歳。母は長生きしてくれたのだが、「東京に連れて行ってほしい」という願いは、ついに叶えてあげることができなかった。
貧乏だとか口やかましいだとかいろいろ書いたけど、なんだかんだいって僕を産み育ててくれた実の親である。感謝してないわけがない。
母が亡くなったと聞いたときは(覚悟していたとはいえ)相当にショックだった。母を困らせたり怒らせたり悲しませたりしたことを思い出しては後悔した。
昨日、母の四十九日の法要と納骨を、東京のお寺で済ませてきた。父のお骨を納めているのと同じお寺だ。きっと今ごろ母は、23年ぶりの父との再会を楽しんでいることだろう。いや、ひょっとしたら母のことだから、高倉健さんや菅原文太さんに目移りしているかもしれない(笑)。
実はこの「幼いころを思い出してみる」というシリーズは、母が亡くなった翌日から、自分の幼いころの姿(つまりは父や母がまだ若かったころの姿)を思い出しつつ、追悼のつもりで書き始めたのだった。
終わってみれば自分の情けない話ばかりだったけど、父と母には天国で、暇で暇でしょうがないときに読み返してもらえたらと思う。そして長男とは違い、反抗的で出来の悪い次男坊だったけど、僕は僕なりに懸命に生きていたことを分かってもらえたらと思う。
ちなみに母の逝去のことは、どなたにもお知らせしなかった。いまこの日記で初めて公開する。どうか非礼をお許しいただきたい。
そして皆様からの永年にわたるご厚情に心より感謝しつつ、幼いころの思い出話を終了とさせていただきます。
読者のみなさん、長らく私的なことにお付き合いいただきまして、まことにありがとうございました。
(完)
幼いころを思い出してみる(21)
2014年12月3日 (水曜日)
ふと思い立ち、10月23日から書き綴ってきた幼いころの思い出話。自己満足で書いてきたのだが、案外いろんな方々にお読みいただけたようで、ちょっと恥ずかしいような嬉しいような……。
でも、そういつまでも続けるわけにもいかない。
考えてみれば、もう1か月以上も身近で起きたことを記録していない。これじゃ、「日記」とは呼べないですね(^_^;)。
ということで、中学生時代の忘れられない出来事をもう少しだけ書いたところで、この思い出話シリーズは終了にしたい。
来週の月曜日(または前日の日曜日)の執筆をもって最終回にしようかと思っている。
どうか皆さん、もう少しだけお付き合いくださいませ。
よろしくお願いいたします<(_ _)>
※本日は早朝会議のため、思い出話の執筆は勝手にお休みします。では、そろそろ行ってきます!
幼いころを思い出してみる(20)
2014年12月1日 (月曜日)
1975年夏。中学生最後の夏休み。初の昇段試験でボロ負けした日から半年が過ぎていた。
僕は、半年前と同じ大分市内の昇段試験会場にいた。
夏の大会はすべて終わり、この昇段試験が、中学三年生の僕にとっての最後の試合だった。
対戦相手は、僕と同じ中学生が一人と高校生が二人だった。
半年前のようなゴツイ大人はいなかった。
なんだかイケそうな気がしていた。
・・・結論から書こう。
善戦空しく、段位獲得に必要な「勝ち越し」とはならなかった。
惜しかった。
全戦引き分けで、「有効」や「効果」といったポイント判定がもしあったなら(当時は優勢勝ちの判定はなかったのだけど)勝っていた試合もあったんじゃないかと思う。
でも不思議なことに、落ち込んだりはしなかった。
「これで俺の柔道も終わったんだなあ……」
どちらかというと、清々しい気持ちだった。
その後しばらくして、顧問の飯倉先生に「話がある」と呼び出された。
「クギサキ、昇段試験受かったぞ、黒帯をもらえるぞ!」
「え?」
耳を疑った。
実は先生が審査委員たちに掛け合って、無理やり?合格にしてくれたのだった。
つまり言うなれば「推薦合格」。柔道界に影響力のある飯倉先生ならではの裏ワザだったのだと思う。
でも、合格は合格。素直に嬉しさが込み上げてきた。
二学期が始まって数日後、合格証書と黒帯が学校に届けられた。
夕方の学活の時に、担任の先生がその証書を読み上げ、僕に黒帯を手渡してくれた。
天にも昇る気持ちだった。
辛くて、シンドいだけの柔道だったが、三年間辞めずにやりつづけてよかったと心から思った。
その日、家に黒帯を持って帰った。
その黒帯を見て、母がどのような反応を示したかのかは残念ながら忘れてしまったのだが、父の反応はよく覚えている。
僕の父親は戦後(予科練から戻った20歳前のとき)東京の警察学校に通っていたことがある。そのとき、柔道も習っていたらしいのだ(父は心臓に持病があり、警官になれぬまま警察学校を辞め、その後板前の修業を始めたのだった)。
「黒帯は、柔道をする者にとって一番の勲章たいね。俺は黒帯ばとる前に辞めてしもうたばってん。キヨヒデ、いやあ、よかったねえ、ようがんばったねえ」
父はそう言って、我がことのように黒帯を触りながら喜んでくれた。
あれから40年の歳月が流れた。
黒帯は、いまでも僕のすぐそばで、僕のことを勇気づけてくれている。
幼いころを思い出してみる(19)
2014年11月28日 (金曜日)
中2の男子にとって母親の存在というのは鬱陶しいものである。特にうちの母親は、なにかと細かいことに口煩いタイプだったので、僕は「はいはい、はいはい」といって無視することが多かった。
しかし、家計を支えるために毎晩遅くまで働いて帰ってくる母を見て、心の中ではいつも感謝していた。
母の作ってくれる弁当はとてもおいしかった。特に母の作る玉子焼きと鶏のから揚げは絶品だった。
柔道の昇段試験の日、母が持たせてくれた弁当は特大で、から揚げが大量に入っていた。ニンニクが効いており、周囲にぷんぷん匂いを漂わせていたことをよく覚えている。
母にとって、僕の柔道着の洗濯は大仕事だった。毎週、土曜日の練習後に持ち帰って、日曜日の朝から母に洗濯してもらうのだが、血や汗やカビが染みこんだ分厚い柔道着には難儀していたようだ。洗濯機は使わずに桶でゴシゴシ手洗いしてくれていた。
昇段試験に落ちて、しょげ返っている僕のことを母がどのように慰めたのか、あるいは励ましたのか、残念ながらよく覚えていない。
が、日ごろ苦労しながら面倒を見てくれている母に対して、柔道を辞めるということを言い出せなかったのは事実だ。
ともあれ、柔道を続けることを決意した僕は、半年後の夏、再度、昇段試験にチャレンジしたのだった。
(本日は短め。次回は柔道物語の完結編です)
幼いころを思い出してみる(18)
2014年11月27日 (木曜日)
辞めてしまおうかと思った柔道だが、結局は続けることになった。なぜだったかは覚えていない。
ひとつ思い当たるのは、母親の存在だろうか。
母は僕が柔道をやることに賛成でもなかったし反対でもなかった。
このころの母は大学入試を控えた兄(京都の予備校で浪人中だった)がいたこともあり、毎晩遅くまで仕事をしていた。
なんの仕事かというと旅館の女中(いまは仲居と呼ばれることのほうが多い)の仕事である。
余談となるが、母の実家は昔旅館を営んでいた。母の父(つまり僕にとっての祖父)は豪胆な実業家で、八代(熊本県)の小さな村のはずれで温泉を掘り当てた。僕が生まれるずっと前の話だが、その温泉を活かした「鶴の湯」という旅館を建てたのだ。
木造三階建ての立派な旅館で、祖父・祖母、母の兄妹・甥・姪たちが大家族で経営にあたり、一時はかなり賑わっていたそうだ。母が父と出会ったのも、この旅館に父が板前として派遣されていたためだと思われる。
そんな母なので、女中の仕事を抵抗なくやることができたのだろう。湯布院には温泉旅館が多数あり、女中の仕事にもすぐにありつけたようだった。
とはいえ、仕事はハードである。
夕方4時ころから旅館に行き、帰宅は早くても夜9時過ぎ。深夜0時を過ぎることも珍しくなかった。勤め先は大きな旅館で、何室もあるお客さんの部屋の夕食の片づけをしたり布団を敷いて回ったり、といった体力をかなり使う仕事だった。
ちなみに、このころの父親の仕事場は、湯布院から遠く離れた熊本の旅館。単身住み込みで働いていたので、家では僕と母の二人暮らし。だから、僕が柔道の部活を終えて家に帰っても誰もいない。母が勤めに出掛ける前に準備してくれていた晩御飯を一人で食べて、テレビを観たり勉強しながら母の帰りを待つ、といった毎日だった。
(ちょっと長くなりそうなので続く)