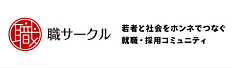幼いころを思い出してみる(21)
2014年12月3日 (水曜日)
ふと思い立ち、10月23日から書き綴ってきた幼いころの思い出話。自己満足で書いてきたのだが、案外いろんな方々にお読みいただけたようで、ちょっと恥ずかしいような嬉しいような……。
でも、そういつまでも続けるわけにもいかない。
考えてみれば、もう1か月以上も身近で起きたことを記録していない。これじゃ、「日記」とは呼べないですね(^_^;)。
ということで、中学生時代の忘れられない出来事をもう少しだけ書いたところで、この思い出話シリーズは終了にしたい。
来週の月曜日(または前日の日曜日)の執筆をもって最終回にしようかと思っている。
どうか皆さん、もう少しだけお付き合いくださいませ。
よろしくお願いいたします<(_ _)>
※本日は早朝会議のため、思い出話の執筆は勝手にお休みします。では、そろそろ行ってきます!
幼いころを思い出してみる(20)
2014年12月1日 (月曜日)
1975年夏。中学生最後の夏休み。初の昇段試験でボロ負けした日から半年が過ぎていた。
僕は、半年前と同じ大分市内の昇段試験会場にいた。
夏の大会はすべて終わり、この昇段試験が、中学三年生の僕にとっての最後の試合だった。
対戦相手は、僕と同じ中学生が一人と高校生が二人だった。
半年前のようなゴツイ大人はいなかった。
なんだかイケそうな気がしていた。
・・・結論から書こう。
善戦空しく、段位獲得に必要な「勝ち越し」とはならなかった。
惜しかった。
全戦引き分けで、「有効」や「効果」といったポイント判定がもしあったなら(当時は優勢勝ちの判定はなかったのだけど)勝っていた試合もあったんじゃないかと思う。
でも不思議なことに、落ち込んだりはしなかった。
「これで俺の柔道も終わったんだなあ……」
どちらかというと、清々しい気持ちだった。
その後しばらくして、顧問の飯倉先生に「話がある」と呼び出された。
「クギサキ、昇段試験受かったぞ、黒帯をもらえるぞ!」
「え?」
耳を疑った。
実は先生が審査委員たちに掛け合って、無理やり?合格にしてくれたのだった。
つまり言うなれば「推薦合格」。柔道界に影響力のある飯倉先生ならではの裏ワザだったのだと思う。
でも、合格は合格。素直に嬉しさが込み上げてきた。
二学期が始まって数日後、合格証書と黒帯が学校に届けられた。
夕方の学活の時に、担任の先生がその証書を読み上げ、僕に黒帯を手渡してくれた。
天にも昇る気持ちだった。
辛くて、シンドいだけの柔道だったが、三年間辞めずにやりつづけてよかったと心から思った。
その日、家に黒帯を持って帰った。
その黒帯を見て、母がどのような反応を示したかのかは残念ながら忘れてしまったのだが、父の反応はよく覚えている。
僕の父親は戦後(予科練から戻った20歳前のとき)東京の警察学校に通っていたことがある。そのとき、柔道も習っていたらしいのだ(父は心臓に持病があり、警官になれぬまま警察学校を辞め、その後板前の修業を始めたのだった)。
「黒帯は、柔道をする者にとって一番の勲章たいね。俺は黒帯ばとる前に辞めてしもうたばってん。キヨヒデ、いやあ、よかったねえ、ようがんばったねえ」
父はそう言って、我がことのように黒帯を触りながら喜んでくれた。
あれから40年の歳月が流れた。
黒帯は、いまでも僕のすぐそばで、僕のことを勇気づけてくれている。
幼いころを思い出してみる(19)
2014年11月28日 (金曜日)
中2の男子にとって母親の存在というのは鬱陶しいものである。特にうちの母親は、なにかと細かいことに口煩いタイプだったので、僕は「はいはい、はいはい」といって無視することが多かった。
しかし、家計を支えるために毎晩遅くまで働いて帰ってくる母を見て、心の中ではいつも感謝していた。
母の作ってくれる弁当はとてもおいしかった。特に母の作る玉子焼きと鶏のから揚げは絶品だった。
柔道の昇段試験の日、母が持たせてくれた弁当は特大で、から揚げが大量に入っていた。ニンニクが効いており、周囲にぷんぷん匂いを漂わせていたことをよく覚えている。
母にとって、僕の柔道着の洗濯は大仕事だった。毎週、土曜日の練習後に持ち帰って、日曜日の朝から母に洗濯してもらうのだが、血や汗やカビが染みこんだ分厚い柔道着には難儀していたようだ。洗濯機は使わずに桶でゴシゴシ手洗いしてくれていた。
昇段試験に落ちて、しょげ返っている僕のことを母がどのように慰めたのか、あるいは励ましたのか、残念ながらよく覚えていない。
が、日ごろ苦労しながら面倒を見てくれている母に対して、柔道を辞めるということを言い出せなかったのは事実だ。
ともあれ、柔道を続けることを決意した僕は、半年後の夏、再度、昇段試験にチャレンジしたのだった。
(本日は短め。次回は柔道物語の完結編です)
幼いころを思い出してみる(18)
2014年11月27日 (木曜日)
辞めてしまおうかと思った柔道だが、結局は続けることになった。なぜだったかは覚えていない。
ひとつ思い当たるのは、母親の存在だろうか。
母は僕が柔道をやることに賛成でもなかったし反対でもなかった。
このころの母は大学入試を控えた兄(京都の予備校で浪人中だった)がいたこともあり、毎晩遅くまで仕事をしていた。
なんの仕事かというと旅館の女中(いまは仲居と呼ばれることのほうが多い)の仕事である。
余談となるが、母の実家は昔旅館を営んでいた。母の父(つまり僕にとっての祖父)は豪胆な実業家で、八代(熊本県)の小さな村のはずれで温泉を掘り当てた。僕が生まれるずっと前の話だが、その温泉を活かした「鶴の湯」という旅館を建てたのだ。
木造三階建ての立派な旅館で、祖父・祖母、母の兄妹・甥・姪たちが大家族で経営にあたり、一時はかなり賑わっていたそうだ。母が父と出会ったのも、この旅館に父が板前として派遣されていたためだと思われる。
そんな母なので、女中の仕事を抵抗なくやることができたのだろう。湯布院には温泉旅館が多数あり、女中の仕事にもすぐにありつけたようだった。
とはいえ、仕事はハードである。
夕方4時ころから旅館に行き、帰宅は早くても夜9時過ぎ。深夜0時を過ぎることも珍しくなかった。勤め先は大きな旅館で、何室もあるお客さんの部屋の夕食の片づけをしたり布団を敷いて回ったり、といった体力をかなり使う仕事だった。
ちなみに、このころの父親の仕事場は、湯布院から遠く離れた熊本の旅館。単身住み込みで働いていたので、家では僕と母の二人暮らし。だから、僕が柔道の部活を終えて家に帰っても誰もいない。母が勤めに出掛ける前に準備してくれていた晩御飯を一人で食べて、テレビを観たり勉強しながら母の帰りを待つ、といった毎日だった。
(ちょっと長くなりそうなので続く)
幼いころを思い出してみる(17)
2014年11月26日 (水曜日)
憧れの黒帯を手に入れるために受けた昇段試験。しかし、その黒帯を手に入れるためには3人の選手と戦って勝ち越さなければならない。
僕の対戦相手は警察学校に通う警官見習い2名と高校生1名。中学2年生の僕からは、とてつもない巨人に見えた。
対戦が始まった。
最初の対戦相手が警官見習いだったか高校生だったかは覚えていない。
覚えているのは「始め!」の審判の合図で組んだ瞬間、僕の体が宙に舞って畳に叩きつけられたこと。
あっというまに一本取られてしまった。ぜんぜん相手にならないとはこのことだ。
二人目との対戦。残念ながら記憶に残っていないのだが、負けたのは間違いない。
そして、忘れもしない三人目との対戦。相手は警官見習いのゴツイ大人だった。
僕はすでに2連敗していたので、もう黒帯の可能性はなくなっていた。戦意喪失の状態だ。
せめて一矢を報いたい…なんていうことは考えていなかったのだが、投げ飛ばされて痛い思いだけはしたくなかった。
だから僕は腰を思いっきり引いた逃げの姿勢をとっていた。警官見習いは足を飛ばしたり投げを打とうとするのだが、逃げに徹している僕には技がかからない。
僕が逃げてばかりいるので警官見習いも頭に来たのだろう。僕をブンブンと力任せに振り回す戦法に出た。
畳の上をぐるぐるぐるぐる。目が回るくらいに振り回された。
そして次の瞬間、浴びせ倒しをくらった。
警官見習いは僕を羽交い絞めにして抑え込む。静かに抑え込んでくれればいいものを、けさ固めしながら体をぐるぐるぐるぐる回転させる。僕の右腕は、そのたびに畳に強烈に擦り付けられていた。
30秒が経過して、抑え込み一本。
負けを告げられた後、審判から「大丈夫か?」と声をかけられた。僕の右腕からは血が滴っていたのだ。柔道着の裾をまくってみて自分の目を疑った。右腕が真っ赤っか。酷い火傷をしたように皮が剥けて腕全体が充血していた。
情けない敗戦だった。
こんな負け方をするくらいなら、素直に投げ飛ばされておけばよかった。
大分市から湯布院に帰る汽車の中で僕は放心状態だった。
試験会場で応急処置をしてもらった右腕。ぐるぐる巻きの包帯の下からジンジンとした痛みが襲ってきていた。
「くそっ、もう柔道なんか辞めてやる!」
その日の夜は、悔しいのと情けないのと痛いのとで、一睡もできなかった。
幼いころを思い出してみる(16)
2014年11月25日 (火曜日)
昇段試験は、筆記試験と実技試験からなる。筆記試験は、柔道修行の目的とか技の種類を書いたりとか、ごくごく簡単なもの。前日に予習をすれば、よほどのおバカでないかぎり満点が取れるもの。
実技試験は、形の演技と試合からなる。形の演技は僕は比較的得意だった。肩車とか背負い投げとか。いまでもできるんじゃないかな。
問題は試合。
4人1グループとなり総当たり戦を行う。ここで勝ち越すことが、段位を取得するための絶対条件となるのだ。
弱い選手たちとの組み合わせであればラッキーなのだが、運悪く強い選手がグループの中に2人いると負け越しが決まってしまう。どういう組み合わせになるのかは、当日まで分からない。
僕が割り当てられたグループは、警察学校に通う大人(警官の見習い)が2名、高校生1名、そして僕。
おいおい、なんだよ、なんだよ……。
いままでは中学生同士でしか試合をしたことがなかったのに、いきなり高校生や大人との対戦。しかも、3人ともごっつい体つきである。
僕は試合前から完全にビビりまくっていた。そして、昇段試験を受けるなんて言ったことを後悔した。
でも、いまさら逃げ帰るわけにもいかない。
僕は足をブルブルガクガク震わせながら、警察学校生と高校生との戦いに臨んだ。
幼いころを思い出してみる(15)
2014年11月21日 (金曜日)
「クギサキ、お前は柔道をやるために生まれてきたようなもんじゃの、練習を続けていたらそのうち強くなるぞ、ガハハ」
・・・と、言われてその気になって、つらい練習にも耐えながら数か月が過ぎていた。
しかし、一向に強くなった自覚がない。
先輩と乱どり稽古(実際の試合のような練習)をしても、いつもコテンパンにやられるばかり。勝てたことなんて一度もなかった。
そんな僕も2年生になり、大会に出なければならない日がやってきた。大分郡の大会で、僕は個人戦に出場することになった。
結果は、惨敗。
詳しい試合内容は忘れてしまったが、とにかくあっという間に投げられたという記憶がある。
弱さを実証してしまった僕は、以来、試合に出ることはほとんどなくなり、もっぱら補欠選手となる。まあ気楽と言えば気楽なのだが、やはり悔しいという気持ちもあった。
柔道といえば、やっぱり黒帯。
黒帯を締めた柔道着姿には、こんな弱い僕でも、強い憧れを抱いていた。
大分県では夏と冬の2回、昇段試験が行われていた。
中2の1月か2月ころだったと記憶している。僕は、昇段試験を受けることにした。
当時の同期部員たち(たしか僕を含めて7名いた)も全員、昇段試験を受けるために、遠く大分市まで朝いちばんの汽車に乗って出かけて行った。
試験場は、大分市内の大きな体育館。
いかにも強そうに見える柔道家たちが、ぎっしりと詰めかけていた。
(果たして黒帯はとれるのか?)