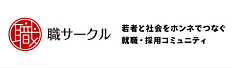幼いころを思い出してみる(8)
2014年11月11日 (火曜日)
結局、僕が買ってもらった自転車は5段変速のスポーツ車ではなく、24インチのお子ちゃま自転車だった。
値札を見てビビッてしまったこともあるのだが、それよりなにより僕はこの日まで自転車に乗った経験がなく、せっかく高い自転車を買ってもらっても自由に乗り回すことなんてできないのではなかろうか、という不安があったからだ。
さらに5段変速の自転車のタイヤサイズは26インチ。当時の僕の背の高さでは、サドルを一番下げたとしても足が地面に届かなかった。自転車屋のご主人にも、「まずは24インチのほうが練習するのにいいんやねーかい?」というアドバイスをもらったのも大きかった。
まあ、何はともあれ生まれて初めての自転車。飛び上がるほどに嬉しかった。買ってもらったのは青い色の、「つつんつつのだ、つつんつつのだ、つんつんつのだのTU号」だった。いまでもその姿かたちはよく覚えている。後輪の泥除けには、僕の自宅の住所と僕の名前がきっちりと書かれていた。自分だけの自転車。まさに愛車を持つことができたのだ。
しかし、その翌日から、辛く厳しい日々が僕を待ち受けていた。
自転車に乗れないのだ。いや、乗り方がわからないのだ。1メートルも進まないうちに自転車は倒れてしまう。
近くの空き地で練習していたのだが、あまりに恥ずかしいので(春休みで閑散としていた)小学校の校庭まで自転車を押していき、ひとりで練習することにした。
2日経っても3日経っても、まったく進歩なし。自分の運動神経のなさに、ほとほと愛想が尽きた。
「おい、クギサキ、よーがんばっちょるの」
後ろを振り返ると、若杉先生がいた。
若杉先生は小学校4年生のときのクラス担任。低学年のころと違い、すっかりお調子者になっていた僕は、先生からいつも怒られていた。つい数日前に終業式を終えたばかりだったのだが、先生に声をかけられて、なんだかとても懐かしく感じた。
「先生、春休みなのに何しよんの?」
「おまえらは春休みかもしれんけど、教師は学校に来んといけんのじゃ。それにしてもおまえ、自転車に乗りきらんかったんやのう。しょうがねーやっちゃの。ほら、先生が押しちゃるけん前向いて漕いでみい!」
先生はそういって、自転車を後ろから押してくれた。
ずっでーん!と、何回も何回も転んだのだが、そのうちなんとなくバランスが取れるようになってきた。若杉先生は一時間以上、僕の自転車の練習に付き合ってくれた。
「よし、あとはおまえひとりでがんばれ。これがおまえに最後にしちゃれることやったかもしれんの。じゃ、元気での!」。先生はそういって、校門から消えていった。
若杉先生とはこの日以来、会うことはなかった。4月の新学期から他の小学校に異動になったのだ。そんなこと、このときには思ってもいなかったのだが、先生は由布院小学校を去ることをすでに知っていたのだろう。
ともあれ、僕は急速に自転車に乗れるようになっていった。
以来、僕はいつも自転車を乗り回していた。まるで背中に羽が生えたように、湯布院の街を北から南、西から東へと、毎日のように自由に漕ぎまわっていた。
ちょうど成長期でもあり、24インチの自転車がみるみる小さくなっていった。
そして僕が6年生に進級するころ、父親が突然、5段変速の26インチの自転車を買ってくれた。どうしたことだろう。パチンコや麻雀で大勝ちしたのだろうか。24インチの自転車を買ってもらったとき以上に嬉しかった。24インチの自転車が子供向けだとすれば、26インチの5段変速は大人向けの自転車。
思春期を迎えていた僕は、この5段変速の自転車のおかげで、大人の仲間入りができた気分になっていた。そして、女の子のことが気になって気になって仕方のない日々を過ごすようになる。
ちなみに5段変速の自転車は、小学校6年生から高校を卒業するまでの7年間、僕の青春をともに過ごした同志なのである。
幼いころを思い出してみる(7)
2014年11月10日 (月曜日)
小学5年生に進級する春休み直前の頃だった。僕の両親は、なんと僕に自転車を買い与えてくれた。
たしか小学3年生の頃いちどだけ母親に、「自転車が欲しい」と訴えかけたことがあった。そのときは「そげんもん買うてどげんすっと! あんたには何のために足があっとね!!」と理不尽に叱られて、それっきりだった。
しかし、どうしたことか、ある日突然「キヨヒデさん、あんた自転車が欲しかって言いよったね。買うてやろか」と、母親から持ちかけられた。欲しいと訴えてから2年以上の月日が経っていた。小学生には10年以上の歳月が流れていたのと同じくらいの感覚だった。
大阪万博に行かせてあげられなかったことを申し訳なく思ったのだろうか……。
まあ、そんなことはどうでもよい。
突然、自転車を買ってもらえることになった僕は、天にも昇るような気持ちだった。
3月の終業式の日だった。学校は午前中に終わり、お昼過ぎ、勤め先の旅館から抜け出してきた父親と小学校のそばにある自転車屋で待ちあわせた。
店内には、ピッカピカに光った自転車がズラーッと並んでいた。
僕はブリジストンの、かっこいい5段変速の自転車が欲しかったのが、値札を見てびっくり。「これは無理だろうな…」と思った。
父親が店にやってきた。
「どれにするね?」と、優しく尋ねてくれた。
我が家の経済状況を十分すぎるくらい理解していた僕は、「五段変速の自転車が欲しい」なんて、とても言えなかった。
(ゆったりと続く)
幼いころを思い出してみる(6)
2014年11月5日 (水曜日)
先々週の木曜日からふと思い立って書き始めたこのシリーズ。小学生時代の思い出をいくつか書いたところで終わりにしようかと思っていたら、昨夜、中学時代の悪友から、「ここまで来たら俺のことを登場させろ!」という投稿がFacebook経由であった。
しょうがない。もう少しだけ書き続けることにしよう(´・_・`)。
—
1969年7月。
僕ら世代にとっては忘れられない出来事があった。
そう、アポロ11号だ。人類が初めて月面に降り立ったのだ。
興奮しながらテレビにかじりついていた。「月にウサギはいるのだろうか…」と、本気で考えていた。なんて純粋でかわいい子供だったのだろう(笑)。
その翌年の1970年。
これまた僕ら世代にとって忘れることのできない大きなイベントが開催された。
大阪万国博覧会だ。
アポロ11号が持って帰ってきた「月の石」がアメリカ館に展示されており、大きな話題を集めていた。
大阪万博には輝ける未来があった。ドキドキわくわくの世界があった。新聞、雑誌、テレビ、ラジオでは、連日のように万博の賑わいを伝えていた。
行きたくて行きたくて仕方なかった。
兄は、中学校の修学旅行で万博に行けることになった。
うらやましくてうらやましくて仕方なかった。
ある日、「一学期の成績が良かったら連れて行ってやる」と、母親から言われたことがある。
勉強は嫌いだったが、一学期の通知表はそこそこ良かった。
しかし、一向に連れて行ってもらえる気配もないままに、夏休みが終わろうとしていた。
意を決して母親に聞いてみた。
「あ、あのー、万博にはいつ行けるとね?」
「あんた、なんばふざけたこつ言いよるとね。万博やら行けるわけなかろがね。どこにそぎゃんお金があっとね?」
ショックだった。
カラーテレビはおろか、冷蔵庫も洗濯機も、電話すらなかった貧乏な我が家である。大阪万博に連れて行ってもらう経済的余裕など、考えてみたらどこにもなかったのだ。
期待した自分が馬鹿だった。
悔しくて悔しくて、こっそり一人で泣いたことを今でもよく覚えている。
(ちょっと一休みしようかな。続く)
幼いころを思い出してみる(5)
2014年11月4日 (火曜日)
人吉市(熊本)から湯布院町(大分)に引っ越したのは僕が6歳になる直前。1966年11月下旬だったと記憶している。
湯布院は、それまでの人吉とは比べ物にならないくらい寒かった。人吉はまだ秋だったのに、湯布院はすっかり冬。それまで見たことのなかった雪が舞っていたことを覚えている。
僕はまだこのとき幼稚園児だったわけだが、湯布院の幼稚園に通うことはなかった。単純に経済的な問題からだろう。朝から晩まで家の中に閉じこもっていた。昼間の話し相手といえば母親だけ。だから小学校に入学するまで、僕には友達が誰もいなかった。
だからだろうか。僕は小学校に入っても引っ込み思案で、いっしょに遊べる友達がいなかった。大分の方言がうまく喋れなかったことも大きい。熊本の言葉と大分の言葉では、イントネーションも含めて全然ちがう。まるで別の国の言葉のように感じたものだ。
家の中では、父も母も兄もみんな熊本弁を喋るものだから、大分弁習得にはかなりの時間を要した。この言葉の壁は存外に大きく、幼心に劣等感を抱いていたものだ。
授業参観や運動会などで母親が学校にやって来るときは特に憂鬱だった。母親は熊本弁で、あたり構わず大きな声で僕に喋りかけてくるからだ。周囲のお母さんたちとも熊本弁で喋りまくる。もう恥ずかしくて恥ずかしくて、その場を逃げ出したくなったものだ。
そんな僕なのだが、小学校2年生にあがるころには、どうにかこうにか大分弁を喋れるようになっていた。友達も少しずつだが増えてきた。
「巨人の星」のテレビ放映が始まり、メキシコオリンピックが開催され、グループサウンズ(沢田研二のザ・タイガース、萩原健一のザ・テンプターズなど)が大流行したのもこの頃だった。
そういえばこの頃、超狭かったそれまでの長屋から、ほんの少し大きめ(といっても6畳二間+四畳半のお茶の間+三畳の納戸)の家に引っ越していた。風呂(しかも温泉)が家にあったことが何より嬉しかった。
そしてこの家には畑もあった。
母親は、この畑を耕しては、大根、ネギ、茄子、トマト、キュウリ、トウモロコシなどを育てていた。僕もよく畑の草むしりを手伝っていた。採れたての熟れたトマトや、不格好で馬鹿でかいキュウリがやたらと美味しかった。そういえば夏のおやつは、いつもトウモロコシだった。売るほどたくさん実っていた。よくもあんなにたくさん育てられたものだと、今思い出してみても感心する。
(次回あたりで最終回にしようかな)
幼いころを思い出してみる(休憩)
2014年10月30日 (木曜日)
我が家は貧乏だったので、カメラという高価な文明機器を持っていなかった。
よって、幼いころの写真がきわめて乏しい。
下の写真は、小学校入学前の写真として唯一手元に残っているもの。いわば、僕にとっての貴重品である。
この日記にデジタルデータとして載せることによって、半永久的に後世に残っていってくれるかな?
けさは日記執筆のための時間が取れなかったので、「湯布院編」の執筆はまた後日。本日はちょっと休憩ですね(^_^;)。
(明日は書けるかな?続く…)
幼いころを思い出してみる(4)
2014年10月29日 (水曜日)
いったい、いつまで続くんだろう…と、自分でも不安になりながら今朝も執筆を続けます(´・_・`)。
—
他にも断片的ではあるが、いろいろと覚えている幼稚園時代の出来事がある。
●当時、住んでいた家には風呂がなく、大きな共同温泉(都会でいう銭湯)に通っていた。しかも女湯に(!)。男女の下半身の造りの違いをいつも不思議に感じていた。
●普段は旅館の仕事で滅多に家にいることのない父親が、その夜は珍しく家にいて、僕の隣で寝てくれた。落語の小噺を面白おかしく喋ってくれた。なんだかとても嬉しくて幸せな気持ちだった。
●七夕の日(7月7日)、幼稚園ではひとりひとりに小さな笹が配られた。色紙をはさみで切って作った短冊に願い事をたくさん書いて、その笹に括り付けた。その笹は各自家に持って帰って親に見せることになっていた。しかし家に着いた時には、括り付けたはずの短冊はひとつも笹に残っていなかった。実は、人吉地方はこの日午後から大雨。笹の短冊は、帰り道に雨に打たれ、すべて流されてしまっていたのだった。当然、家で大泣きして母親を困らせた。
●当時、幼稚園には毎日お弁当を持って行っていた。ジャングル大帝のイラストが施された、お気に入りのお弁当箱だった。うちの母親の作る弁当は美味しかった。しかし、その日の弁当だけは、なぜかとても不味かった。理由は分からないが、びっくりするくらいに不味かった。全部食べることができず残してしまった。先生から怒られた。僕は悲しくて大泣きした。先生から怒られたからではない。いつもは美味しいはずの弁当が、食べられないくらいに不味かったことが悲しかった。弁当に残ったおかずやご飯を母親に見せてはいけないと思い、帰り道、川に捨ててしまった。
●夏休みに、家族みんなで旅行をした。(たぶん)生まれて初めて動物園に連れて行ってもらった。ライオンやトラやキリンの実物を見て、感動した。それ以上に、家族みんなで一緒に出掛けられたことが、とても嬉しかった。
●休みの日、朝から一人で留守番をしていた。夕方になっても誰も帰ってこなかった。大泣きした。暗くなってやっと母親が帰ってきた。腹ペコだった。肉なしカレーライスを作ってもらった。不味かったけど幸せだった。
—
これらは、1966年4月から11月までの、約8か月の出来事。正確かどうかは分からないが、50年近く僕の記憶の中に生き残っていた他愛もない出来事の欠片である。
さて、人吉(熊本県)の幼稚園時代の話はこれくらいにして、次回からは湯布院(大分県)に移り住んでからの話を書いてみたいと思う。
(懲りずに続く)
幼いころを思い出してみる(3)
2014年10月28日 (火曜日)
5月の初夏の陽気の日だった。幼稚園が終わり、いつもどおり帰りのバスに乗った。
なんだかボウっとしていた。バスを降りて家まで歩いていた。自分の影がゆらゆらと踊っていた。自分の頭もくらくらしていた。
「あれ?なんだかおかしいぞ」。自分でも気が付いていた。
フラフラしながら自宅までやっと辿り着いた。でも、母親は勤めに出ていて家には誰もいない。玄関の土間から靴を脱いで部屋に上がり込む力はすでに残っていなかった。
ここでいったん記憶は途切れる。
目が覚めた時には布団の中にいた。片側には白衣をまとったお医者さんと看護婦さんがいた。そして反対側には心配そうに覗きこむ母親の顔が見えた。
本当に不思議なのだが、この目覚めた瞬間の景色は、この50年近くずーっと頭の中に焼き付いている。
病名は、あとから知ったのだが、はしか(麻疹)に罹っていたのだ。倒れた日から数えて完治するまで2週間ほどかかった。
久々に幼稚園に行けることになった日のこと。季節は、もうすっかり夏になっていた。
病み上がりということもあり、母親が仕事を休んで付き添ってくれた。
緊張しながら幼稚園の門をくぐった。
園児たちが遊んでいる姿を見てショックを受けた。僕が着ている制服と違うのだ。
僕がはしかで休んでいる間に衣替えとなり、制服制帽が夏物になっていたのだが、そんなこと5歳の僕が知る由もなく、悲しくて泣きだしそうになった。
教室に入った。なんだか皆がよそよそしく感じた。
でも、先生は久々に登園した僕を見て喜んでくれ、制服の違いで受けたショックも和らいできた。
しかし、その数分後、さらなるショックを受けることになる。
先生がオルガンを弾き、園児全員での「朝の唄」が始まったのだが、僕の知らない唄だった。僕が休んでいる間に教えられたと思われる「新曲」だったのだ。
一生懸命、他の園児の口の動きを真似しながら歌おうとするのだが、ついていけない。悲しくて悲しくて、ついに僕はワンワン泣き出してしまった。
大泣きしている僕を見て、先生はやっと気が付いてくれた。オルガンを中断して、僕のところに駆け寄って来た。
「ごめんね、クギサキ君、この歌まだ知らなかったんだよね、ごめんごめん」
母親も、僕の泣き方があまりに酷かったので、心配そうに駆け寄ってきて頭をなでてくれた。
どうってことのない5歳児の1シーンなのだが、人間というのは不思議なもので、こんなことを50歳を過ぎた今でも覚えているのだ。
(次回に続く。明日は書けるかなあ…)