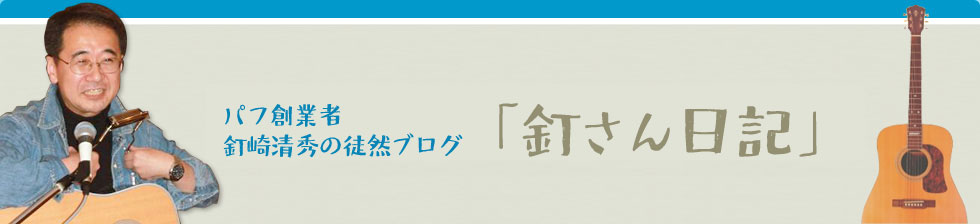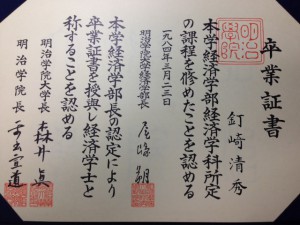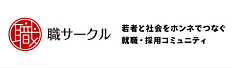ドラマ『LEADERS』をみた。
2014年3月24日 (月曜日)
一昨日、昨日と、2夜連続で放送されたTBSのスペシャルドラマ『LEADERS』。トヨタ自動車の創業者、豊田喜一郎をモデルとして描いた骨太なドラマだった。
ドラマなので全部が全部、史実通りではないのだろうが、「世界のトヨタ」をゼロから築きあげた男たちがいたということに違いはない。この男たちがいなければ、戦後日本の奇跡の復興はなかったかもしれないのだ。
ところで、「機屋(はたや)に貸せても、鍛冶屋には貸せない」とは、住友銀行(ドラマの中では西国銀行)の名古屋支店長が倒産の危機に瀕していたトヨタ自動車の経営陣に言い放った台詞だ。ちなみに機屋というのはトヨタの母体である豊田自動織機のこと。
「お前らは機織り機だけ作ってればいいものを、自動車なんかに手を出すからこんなことになるんだ」という、(必死に踏ん張っていたトヨタ自動車の経営陣にとってみれば)最大の侮蔑の言葉だった。資金繰りを任されていた経理部長はその後、心労で命を落としてしまった。
これは実際にあったことらしく、トヨタ自動車の歴代の経営者は、この時のことをずっと恨みに思っており、住友銀行との取引を(三井と合併して三井住友銀行になるまでの長い間)ずっと拒み続けてきたらしい。規模こそ違えど似たような経験のある僕は、なんだかとても共感してしまった(苦笑)。
結局、日銀が(中央銀行としては異例のことだったのだが)救済に乗り出すのだが、その条件が社員の解雇。1,600人の社員たちの首を切らなければ融資を受けることができない。副社長、総務部長は「会社存続のためにはやむを得ない」と、解雇者のリスト作りを進めるが、その作業が組合員に漏れてしまう。そして、元々仲間同士だった社員たちが経営側と組合側に分かれて大きな労使紛争に発展。「家計が厳しいからと言って家族を追い出す家がどこにある!」と、社員の解雇を拒んでいた喜一郎だったが、最後は自ら断腸の思いで希望退職者を募ることに。そして自分自身も社長の職を辞することを決断する。
事業に情熱を燃やしてきた創業者。会社存続の責務を負う経営陣。会社生き残りの鍵を握るバンカー。事業をゼロからつくってきた古参社員。従業員の雇用を守らなければならない組合幹部。解雇される側の従業員…。
それぞれの立場になってこのドラマを眺めてみると、それぞれ違った見え方となるかもしれない。誰のための何のための会社なのか、事業なのか、銀行なのか。そんなことを考えさせられた。ひとことで言うならば「人の幸せのため」ということになるのだろうが、企業の大小に関係なく、経営や人事に関わる人たちの共通の課題だろう。
そういえば先週、非正規社員1万6,000人を正社員化すると発表したユニクロ(ファーストリテイリング)の柳井さんが社員に語った長いスピーチも、同じようなことを考えさせられる内容だった(全文がこちらに掲載されている⇒ http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20140319/261421/?P=1&rt=nocnt )。
おっと珍しく朝っぱらから真面目なことを書いてしまった。ちょっと似合わないな(笑)。
さて3月も大詰めの週。春に切り替わる週。プロ野球も開幕する週。節目の週の始まりだ。実は、鼻風邪なのか花粉症デビューなのか、よく分からないけど鼻水が大量に流れており、鼻の頭が赤くなっている。とりあえずマスクで鼻を隠したうえで行ってきます!
卒業証書
2014年3月20日 (木曜日)
昨日、娘の卒業式に参加したあとの帰り道で、偶然だがYahooニュースでこんな記事を発見した。
THE ALFEE 40年越しで明学大“卒業” 高見沢「武道館より緊張した」(スポニチアネックス)
アルフィーと同じ大学(明治学院大学)の出身で、しかも今でも母校とは密なお付き合いをしている僕としては、なんだかとても嬉しくて思わずFacebookでシェアしてしまった。
娘の卒業式に感化されたということもあるんだけど、「そういえば自分の卒業証書ってどこだっけ?」と、夜中に自宅の書棚を漁ってみつけた丸30年前の卒業証書がこれ。
卒業式の記憶というのは実はあまりない(すでに働いており、式には仕事の合間を縫ってバタバタと参加した)のだが、こうやって卒業証書を眺めると、感慨深いものがある。埃を払って、もっと大事に仕舞っておかなきゃ。
大学って(いや大学だけに限らず、中学でも、高校でも、職場でも)どこで学ぶかということよりも、何を学ぶか、誰と学ぶか、どう学ぶか、ということが大事なんだと思う。卒業証書を眺めていて、卒業した、という事実ではなく、在学中に過ごした(あれこれぎっしり詰まった)日々を振り返ったときに、感慨深くなるのである。
いやあ、卒業証書っていいもんですね。
さて、本日は朝から夜まで、打ち合わせだったり来客だったり就職相談だったりがギッシリだな。
感慨に耽ってばかりもおられませんな(^^ゞ。
では、朝食後ウォーキングで行ってきます!
あっというま
2014年3月19日 (水曜日)
昨日は会社で朝礼を済ませたのち、すぐに東京駅へ。9時40分の新幹線に乗って仙台に向かった。
お客様の会社説明会が仙台で開催されることになっており、そのお手伝いをするためである。
仙台に到着したのが11時34分。乗車時間は2時間足らず。あっというまの到着である。
帰りはさらにあっというまだった。
仙台発が18時19分で東京着が19時52分。乗車時間は1時間33分。驚きの速さだ。
こんなに近くなってしまっては、なかなか一泊するのも難しい。国分町も遠くなりにけり、である(苦笑)。
さて、今朝は早朝会議。日記も朝食も、あっというまに終わらせて出かけなきゃ(^^ゞ。
そうそう。本日は娘の大学の卒業式。会議が終わり次第、会社を抜け出して覗きに行こうと思っている。創業当時、幼稚園児だった娘が早、大学卒業。こちらも、あっというまだった。なんだか感慨深い。
ではでは、遅れないように行ってきます!
遅刻をしてはいけません
2014年3月18日 (火曜日)
昨日の最後の訪問先は、僕の家のすぐ近所。我が家から歩いて15分~20分くらいのところ(晴海方面)でのアポイントだった。
初めて行くところだが、日ごろのランニングコースでもあり、だいたいの場所の見当はついていた。
・・・つもりだったのだが、読みが甘かった。
5分前には着くように向かったのだが、意外と駅から遠くて、当該の場所までたどり着くのに予想以上の時間を要してしまった。
おまけに「ここだろう」と思っていた場所に、その会社のビルがなかった(実際には、そんなに外れてはいなかったのだが)。
やっと見つけたビルだったのだが、受付のフロアを(関連会社がいくつも入っていたため)間違えてしまい、さらにてんてこ舞い。
結局、着いたときには約束の時間を3分オーバー。おまけに顔面からは汗が噴き出す始末。あー、やっちゃった(;´Д`)。
いくら見知った土地であっても、初訪問の際にはきちんと下調べをして、時間には余裕をもって行かなきゃね。
・・・と、営業マンとしては初歩的な失敗。反面教師的な役割を演じてしまった昨日の訪問なのでした。
え、きょうの日記はこれだけ?
はい、ちょっと急ぎの仕事があるので、これだけ(^^ゞ。
本日は、会社での朝礼後すぐに仙台に行く。日帰りだけど、仕事が終わったらちょっと寄り道しようかな。愚か者にならない程度に(笑)。
では仕事&朝食後、行ってきます!
弱い者いじめをしない
2014年3月17日 (月曜日)
パフ社員の行動指針にもなっている「う・ま・れ・よ」。
「うそをつくな」、「まけるな」、「れいぎただしく」、「よのため人のため」なのだが、最後の「よ」の、もともとの意味は、「よわいものいじめをするな」だった。
最近では、この「よわいものいじめをするな」も復活させる必要があるのではないかと感じることがよくある。
この「う・ま・れ・よ」。16年前、パフをつくったばかりの僕に伝授してくれたのが、(このたびJリーグチェアマンに就任した)ムライさんだった。
浦和レッズサポーターが起こした差別的横断幕問題に対して、先週ムライさんが発表した処分。そして記者会見で説明していた内容は、まさにこの「う・ま・れ・よ」に基づくものだった。特に「よわいものいじめをするな」の精神に則っていたのではないかと思う。
記者会見の際、記者からの質問にムライさんはこう答えている。
――(記者)これまでは裁定委員会を開き、解決するまで時間を要していたが、今回は迅速な対応だった。これは人種差別行為に対して重大に受け止めていることの表れなのか?
(ムライさん)私はチェアマンとして男性でも女性でも、お年寄りでも子供でも1人でも多くの新たなお客さんをスタジアムに迎え入れたいと思ってやってきております。これは私の基本方針でもあります。もちろん外国人のお客さんでもよくて、さまざまな人に来ていただきたい。そのため今回のような出来事は私の方針と真逆な話でありました。さまざまな意見があると思いますが、私の判断としてJリーグの意思を早く伝えたいということがありました。
それからJリーガーは子供たちがなりたい職業のナンバーワンだったりもします。多くの子供たちに仲間外れはやってはいけないということを伝える責任もあって、多くの関係者にメッセージを伝える意味もあります。Jリーグの100年構想や理念はサッカーに限らない、豊かなスポーツ文化を広げようという信念があると私は理解していて、仲間外れはしてはいけないんだということを子供たちに伝えたいという思いがありました。(スポーツナビの記事より引用)
就任早々起きたこの難事に対して、ムライさんは、とてもムライさんらしいヒューマンで迅速な判断と対応を行なった。
今回の裁定を批判する人たちもいるし、逆恨みの言動をとってしまう心ない人たちも一部いるかもしれない。でもムライさんには、そんなことに屈せず毅然とした態度を取り続けてほしい。もちろん僕がそんなこと言わなくても、ムライさんはいつでも毅然としてるに決まってるんだけど(^^ゞ。
問題は僕らのほうだ。「うまれよ」の意味するところを、もっともっと社員をはじめとする仲間たちに浸透させなければならないし、その精神に反する者に対しては断固たる措置を取らなければならない。今回の記事を読んでいて、「おまえもしっかりやれ!」と、ムライさんから叱咤されているような気持ちになった。
さて、3月も後半である。昼間はすっかり春めいてきた。新しい週のはじまり。ウォーキングでゆっくり体をほぐしながら、行ってきます!
就活生との面談
2014年3月14日 (金曜日)
昔、「パフの就職相談室」という掲示板形式の相談コーナーが、パフが運営するWebサイト(パフの就職応援ページ)のなかにあった。創業直後の1998年から5年間くらい運営していた人気コンテンツで、この掲示板を訪れる学生は1日に数百人はいたのではないかと思う。
Webだけではなくリアルの場でも就職相談を受け付けることが多かった。土、日を利用して多くの学生の個別の相談に応じていた。もちろん、これら活動はお金を稼ぐための事業ではない。ただ、学生の現実を知り、学生を通して企業の採用の実態を知るうえでは、とても価値ある活動だったと自己評価している。
現在では、この「就職相談室」に代わるものが御茶ノ水で運営している「キャリぷら東京」だったりするのだが、僕自身は最近、学生の相談に応じることがめっきり少なくなってしまった。創業当初は僕も30代後半で、学生の「アニキ」みたいな感覚でいられたのだが、現在では学生の親以上の年齢になり、「説教臭いオヤジ化」してしまったことを自分自身感じていることが原因だ。
そんななか、昨日は久々に学生の個別相談に応じることになった。
パフがお世話になっているお客様からのご依頼で、「友人の息子が困っている。ぜひクギサキさんに相談に乗ってほしい」というリクエストをいただいた。「ご指名とあらばお引き受けしましょう!」と、二つ返事で相談役を買って出た。まあ、学生の相談に乗るのは、もともと嫌いではないのだ(^^ゞ。
約1時間の面談。学生からの相談は、思わず説教したくなるような内容だったのだが、当の学生にしてみれば真剣に悩んだうえでの相談。「説教しちゃいかん!」と自分自身に言い聞かせながら、諭すように話をしたのだが、どこまで学生に伝わったのだろうか。いま振り返ると、学生には「オヤジの説教」に聞こえてしまったかもしれない。逆にもう少し厳しく伝えたほうがよかったかも、と思う部分もある。ちょっともどかしい。不完全燃焼な面談をしてしまったという反省がある。
僕は今まで、CDAやGCDFといったキャリアカウンセラーの資格にはあまり関心はなかったのだが、(いまでも資格取得そのものには関心がないのだが)ちょっと体系だった勉強をしなきゃあかんかなあ……と思ったりもしている。
同業仲間でも、キャリアカウンセラーの資格を持っている人たちが増えてきた。いっちょやってみようか。いや、まだ宣言したわけではない。少し考えてみようかな…ということを書き留めるだけに本日のところはしておこう(;^ω^)。
さて、本日は年齢差35歳の、高校3年生(4月からの大学1年生)向けの講演の日。これもちょっと手強いぞ。説教臭くならないように、かといって迎合しないように、伝えたいことが伝わるように頑張ろう。
ではでは、そろそろ行ってきます!
大学生に教えてもらった日
2014年3月13日 (木曜日)
昨日は、大分県の別府市で所用を済ませたのち、県内の大学に通うT君に会った。
T君は一昨年の夏、わざわざ大分から東京に出てきて、パフでのインターンシップを一週間ほど行っていた学生。僕が直に会うのは約1年半ぶり。この春からは、東京の某ベンチャー企業で社会人デビューすることになっている。このたび僕の九州出張を聞きつけて、「お会いしたいです!」という連絡をくれたのだ。
しばしT君と歓談したのち、僕が明日、某大手予備校で講演する内容(講演対象は、この春から大学生になる予備校の生徒たち)について相談してみた。
講演では、「入学後、どんな大学生活を送るべきか」という話をすることになっているのだが、具体的な話の内容についてはいろいろと思案しており、いまだに決定打が見つかっていない。
僕が大学に入学したのは、もう30年以上も前(正確には34年前)のことなので、自分の経験を話しても、今の生徒たちにはほとんど参考にならないだろうなあと思っていた。
そこで、「ここは大学生活を終えようとしている現役大学生に聞くのがイチバンだ!」と思ったのだ。
聞いてみて大正解。
うんうん、なーるほどねー、ああ、やっぱりそうなのかあ、という感じ。
そういえば、自分が高校を卒業して、浪人生活を経て大学生になったときもそうだったことを思い出した。
そして大学生活を充実させることができたのも、やっぱりそう。T君の言う通りだった。
ネタバレになるので詳しいことは書かないけど、30数年経った今でも大切なことには普遍性があるものだ。
僕もそうだったけど、やっぱり、大学に入学した直後の1週間が大事。ここで勇気を出して行動するかどうか。そこだな。
そういう意味では、僕に講演を依頼した某予備校の試みは、とても意義があること。「予備校つぶれろ」と言っている高名な方もおられるそうだが、そりゃちょっと言い過ぎだろう。
大事なことを教えてくれたT君、ありがとうございました。おかげで今夜はぐっすり眠れそうです(笑)。
さて、では本日は教えてもらったことを整理するために、原稿として書き起こしてみることにしよう。
ではでは、忘れてしまわないうちに行ってきます!